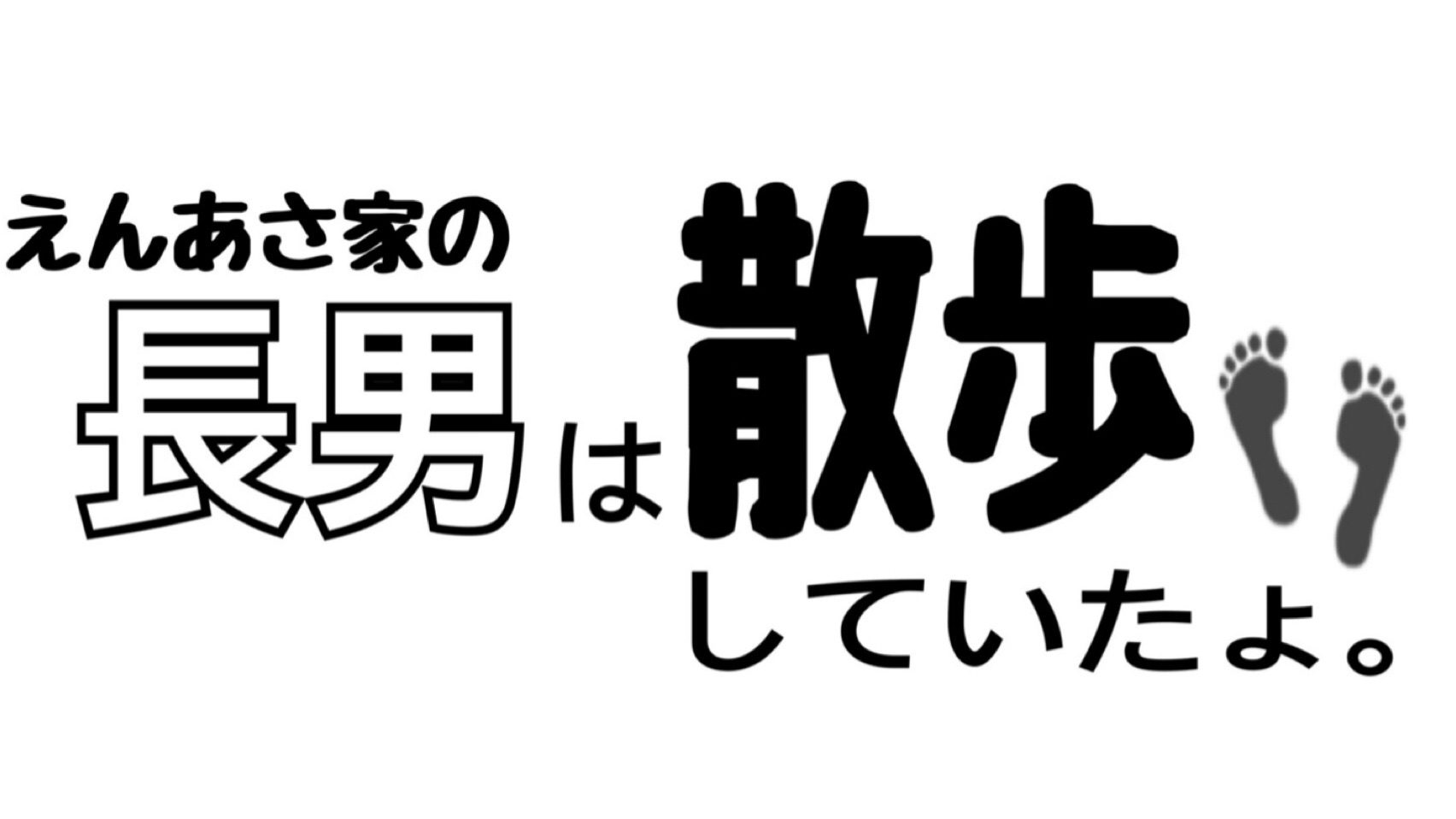「不登校」
この言葉は一般的に否定的な意味合いが強い「不」の文字がはいることによって、どうしてもマイナスイメージが先行してしまう気がして経験者が近くにいる身としてはあまりしっくりきませんし、好きではありません。
わたしの時代は「不登校」ではなく「登校拒否」と言われていました。
「登校拒否」は本人の意思が強く含まれている感じがしますね。
どちらにせよ、
- 学校に行きたくない
- 学校に行けない
本人、または本人を含めたまわりの人間関係において、その子がそう感じる問題点があるわけです。
その問題点を解決しようと一生懸命考え抜いた結果が「学校に行かない」ってことなだけで、決して悪いことではありません。
むしろ、自身の悩みに向き合って、ちゃんと答えを出している。すばらしいことです。
しかしながら今の日本は、「ふつう」は、毎日学校に通うし、小学校・中学校の義務教育を終えたら高校へ進学することが「ふつう」。だから学校へ行かないことは「ふつう」ではない。
そのような常識が本人をはじめ、ところどころに染みついているので「学校へ行きたくない」「学校へ行けない」子どもたちは、本音を吐き出すことにものすごくパワーを使い、やっと伝えられたころには疲弊しています。
正直に申し上げると、親であるわたしもこの「ふつう」に飲み込まれていました。
「ふつう」に学校へ通ってくれることが親としては安心だったからです。
ですが当然、子どももひとりの人間であり個性があります。「学校へ行かない」選択をした、それがその子の個性(考え)であって、「悪」ではない。
学校へ行かなかった人もさまざまな場所で活躍しています。
不登校目線からのきれいごとのように聞こえるかもしれませんが、長男が経験してくれたから「不登校」について考える機会ができ、成長させてもらいました。
学校にへ行かずに休息時間をとることは怠けているのではなく、少なくとも今抱えている不安や問題解決のためにじっくり自分と向き合いながら力を蓄えている時間ですので、どうか見守ってあげてください。
親も子も、自分たちが出した答えに自信を持って、あの時経験したから大丈夫!と胸を張れる未来が訪れますように。
「不登校」は悪いことではありません。
いろいろな意味で「不登校」がなくなることを願いつつ、「不登校」を「散歩」に置き換えてこのブログを綴りたいと思います。
浅川 えん